今回は松本敏治先生の著書をご紹介します☺️
タイトル:自閉症は津軽弁を離さない リターンズ
人の気持ちがわかるのメカニズム
著者:松本敏治
発行:KADOKAWA
初版:令和5年8月25日
松本先生が、奥様から、
自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんたちが津軽弁を話さない
というお話を聞いたことから始まった、
自閉スペクトラム症のお子さんたちの言語習得についての研究📘
前著「自閉症は津軽弁を話さないー自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く」
にまとめられており、こちらもとても面白かったです!
本書は、「ASDのお子さんの中に方言を話すようになる子どもがいる🙄」
という事実を知った先生が、さらに研究をすすめた研究成果がまとめられています。
結論から言うと、めちゃくちゃ面白かったです!😄
なぜかというと、先生の情熱がすごいからだと思います🔥💪
他の人が気にも留めないような研究、
何の役に立つのか分からない研究
だけど、ご自身の純粋に「ただ知りたい!」
という気持ちに従ってひたすら進められ、
他の人には真似できないような研究をなさっているのです。
ASDと定型発達(TD)の子の言語習得の違い、
方言の役割、
普段使っている言葉がどのような意味合いを持っているのかなどなど‥
色々な視点から研究されています🖊️

中でも印象に残ったのは、
TDの子がなぜ、似たような考え方、社会的振る舞いを身につけるのかが
述べられている部分です😳
TDの人が発達とともに個別の個性や感受性の差からくるオリジナルな世界を打ち捨て、均質化・収束化した世界へと移行していくなか、ASDの人はなおも自らの特性や感受性に依拠しながら世界・社会と対峙しているともいえるでしょう。
第13章 もしも自閉スペクトラム症の子が25人、定型発達の子が5人のクラスがあったとしたら
私はこの文章を読んで
どきっとしてしまいました🫣
先生は、TDと言われる人たちは、
ある意味で自分のオリジナルを捨てているのだ
といいます。
ASDの方々は少数派で、
いわゆる「空気を読めない」ASDの人たちが
生きにくいといわれる社会。
そこは自分のオリジナルを捨てている人たちの集まりともいえます。
ASDの人たちは
もしかすると
いつも「本来の自分」
で生きているだけなのかもしれません。
それがいわゆる「社会の常識」🧐
とぶつかるから、
社会で上手く立ち振る舞えないことが多いのかもしれません。
多分TDの中にも、
「本来の自分で生きたい」
と思う人はたくさんいるのではないでしょうか。
だけど世間の目を気にして、本当の自分が出せないのかもしれません。
TDが獲得する社会的な考え方や振る舞いは
社会生活を行う上で確かに重要だし便利ですが、
そこにこだわってしまうと、
ある意味で
逆に自分を苦しめるものになるのかもしれない
そんなことを思いました。
そして自分にとっての常識が
必ずしもそうではないのだ(例えばTDの常識がASDの人にとっては常識ではない。あるいはその逆も。)
ということも、改めて思いました。
内観で「自分の常識を疑う」
ことを教わりましたが、
ASDの人とTDの人の違い
という観点を本書から学びました📚✨
そして、
先生はまた新しい研究テーマを見つけられ、
まだまだこの研究は続くそうです‥🤓
次の本も楽しみです😊
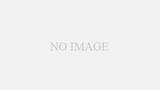
コメント